
こんにちは、さいだーです。

こんなお悩みを解決します。
✔本記事の内容
・コード進行に必要なコード知識
・コード進行の作り方
・コード進行を深く考えて作る場合
・コードセンスの磨き方
・コード進行のオススメ本
・王道進行の紹介
・音楽理論の必要性
✔信頼性
記事を書いている自分は、
youtubeや本なので独学しながら作曲を3年半ほどしています。
✔前置き
本記事では「コード進行がわからない」方に向けて、”コード進行とは”について解説していきます。
この記事を読んでいただければ、
コード進行の作り方やルールを簡単に理解できるようになり、王道進行も紹介するので、コード進行で悩むことはなくなります。
コード進行とは
コード進行とは、
役割を持つ3和音のコード、4和音のコードを繋ぎ合わせてコードの動きを進行させるもの。
このことから、
コード進行は作曲をする曲の動き、曲をどう進めていくかなど曲の基盤となる働きをするので、必要不可欠な要素となってきます。
そして、

と次にコード進行の作り方を知りたいと思いますが、まずその前に必要なコード知識を紹介していきます。
コード進行に必要なコード知識
コード進行に必要なコード知識は、
・コードを繋ぎ合わせる
・メジャーコードとマイナーコード
・3和音のコードと4和音のコード
・コードの役割
この4つのことが重要となるので、
次にこの4つに事について解説していきましょう。
コードを繋ぎ合わせる
コードを繋ぎ合わせるとは、
例えば単体のコード"C、Am、Dm、G"があったとします。
これを一つの塊にして、
C|Am|Dm|G
このように繋げるとコード進行になるので。
コード進行を作成するときは、複数のコードを繋ぎ合わせて作るという考えを持って作りましょう。
そして、コードには、
・メジャーコード
・マイナーコード
主にこの2つの種類に分けることができコード進行を作る上で必要な知識となってきます。
メジャーコードとマイナーコードの違い
メジャーコードとマイナーコードとは、
全音、半音の音程の並びを表す種類の1つ。
メジャーコードとマイナーコードの表記は、
・メジャーコード:M(単体だと表示されない)
・マイナーコード:m
M、mと表記されます。
上記で紹介した”C|Am|Dm|G”の4つのコードを、メジャーとマイナーに分けてみると、
・メジャーコード:C、G
・マイナーコード:Am、Dm
このように分けることができます。
メジャーコードとマイナーコードについて、もっと知りたい方は別記事で解説していますので下記に貼っておきます。
-
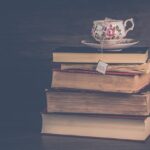
-
メジャーコードとマイナーコードの違いは2つ【簡単な覚え方も】
続きを見る
3和音のコードと4和音のコード
3和音のコードとは、
スケールを1つ飛ばしで3つ重ねたコード。
4和音のコードとは、
スケールを1つ飛ばしで4つ重ねたコード。
この3和音のコードと4和音のコードは、コード進行では必要な知識となってくるので覚えておきましょう。
もっとく詳しく知りたい方は別記事で解説していますので下記に貼っておきます。
-

-
【難しい人向け】ギター打ち込みのコツ4つ【ジャカジャカ音など】
続きを見る
-

-
【役割は3つに】ダイアトニックコードとは【一覧表や使い方など】
続きを見る
コードの役割
コード進行を作るうえで重要な事は1つ、コードそれぞれの機能を理解することです。

と疑問に思うので説明すると、コードにはそれぞれ機能があり、
・トニック
・ドミナント
・サブドミナント
の3つの機能に分類されます。
この3つの機能を理解すると、
意味があるコード進行を作ることができるので、
トニック、ドミナント、サブドミナントは勉強した方がいいと考えています。

という方のために、
トニック、ドミナント、サブドミナントは別記事か解説していきますので下記に貼っておきます。
-
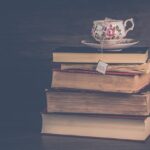
-
トニック、サブドミナント、ドミナントとは【覚え方、代理コードなど】
続きを見る
この4つの知識を頭に入れたら、次にコード進行の作成方法について解説していきます。
コード進行の作り方
コード進行の作り方には一応手順があります。
コード進行の作成手順は、
①キーを考える
②ダイアトニックコードにする
③小節間で考える
④基盤のコード進行を作る
この4つの手順でを踏んで作成すると、楽にコード進行を作成することができます。
次に詳しくやっていきましょう。
①キーを考える
まずはキーを考えてください。
ここで言うキーは、
Cメジャースケールなどのスケールとキーの事を指しています。
どのキーで作成するか考えたら次にダイアトニックコードにしていきましょう。
-
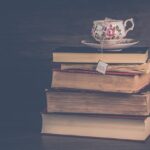
-
ダイアトニックコード一覧表【三和音、四和音】
続きを見る
②ダイアトニックコードにする
先ほど考えたキーをダイアトニックコードに変換して下さい。
ダイアトニックコードの構成、
ⅠM7、Ⅱm7、Ⅲm7、ⅣM7、Ⅴ7、Ⅵm7、Ⅶm7(♭5)
そして、

という方は別記事で解説していますので下記に貼っておきます。
-

-
【役割は3つに】ダイアトニックコードとは【一覧表や使い方など】
続きを見る
③小節間で考える
コード進行を作成する前に、小節間も考えましょう。
基本的には、
4小節、8小節
この2つの小節間で始めは考えると楽なのでオススメです。
小節間を考えたらコード進行を組んでいきます。
④基盤のコード進行を作る
後はダイアトニックコードの7つのコードの組み合わせるだけでコード進行ができます。
例としてC、Dm、Em、F、G、Am、Bm(♭5)でコード進行を組んでみると、
C|Am|Dm|G
このように考えることができたらコード進行の完成です。
ダイアトニックコード+Cメジャースケール=C|Am|Dm|G
しかし、この考えだけでは、

と意味もなくコード進行を作ったことになるので、次にコード進行を深く考えて作る場合の解説もしていきます。
コード進行を深く考えて作る場合
コード進行を深く考えて作る場合は、
・背景のストーリー
・役割を意識する
・強進行を意識する
・ノンダイアトニックコードを使う
この4つの事を意識すると個性のあるコード進行を作成するとができます。
次に詳しく見ていきましょう。
背景のストーリー
コード進行は、
コード進行は作曲をする曲の動き、曲をどう進めていくかなど曲の基盤と上記で説明しました。
このことから、
コード進行を背景のストーリーを考えて作成すると、曲の動きがより明確になるので、
メロディなどが作成しやすくなったり、自分が作成したい雰囲気の曲を作ることができるので、ストーリーを考えて作成しましょう。
役割を意識する
2つ目は、役割を意識することです。
役割とは先ほど説明した
・トニック
・ドミナント
・サブドミナント
この3つの事です。
この3つにはケーデンスがあるので、それを考えて作成すると深いコード進行が作成できます。
強進行を意識する
強進行とは、
完全4度上(または完全5度下)に進むコード進行
この強進行は、
様々の曲のコード進行に使われるもので、強進行を使用すると聴き馴染みのあるコード進行を作成できて、安定的なコードを作成できます。
強進行については別記事で解説していますので下記に貼っておきます。
-
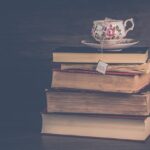
-
強進行とは、なぜ完全4度上に進むの?【弱進行なども紹介】
続きを見る
次にノンダイアトニックコードについてやっていきます。
ノンダイアトニックコードを使う
ノンダイアトニックコードとは、
ダイアトニックコードにないコードの事。
ダイアトニックコードにないコードを使用することで、個性的なコード進行を作成できるようになり、良いスパイスとなると思います。
ノンダイアトニックコードには、
・セカンダリードミナント
・モーダルインターチェンジ
など様々なものがあります。
ノンダイアトニックコードについては別記事で解説していますので下記に貼っておきます。
-
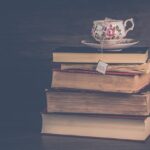
-
ノンダイアトニックコードとは【使うときの考えはスパイス】
続きを見る
コード進行のセンスを上げる方法
コード進行のセンスを上げる方法は、
・曲のコード進行を分析する
・リハーモナイゼーション
この2つをするとコード進行のセンスが上がります。
2つの解説をすると。
曲のコード進行を分析する
曲のコード進行を分析するとは、
例えば「この雰囲気の曲良いな」と感じたときに、コード進行を分析することで、
・この雰囲気にはこのコード進行を使えばいいんだ
・このコード進行のテクニックいい
などと自分に必要なコード進行の知識をピンポイントで吸収できるのでお勧めです。
次にリハーモナイゼーションについてやっていきます。
リハーモナイゼーション
リハーモナイゼーションとは、
元のコードを別のコードに変えること。
これができるようになると、コードの関係性なども理解できるようになるのでお勧めです。
コード進行のセンスを上げたい方は、この2つの事を意識して毎日やりましょう。
コード進行のオススメ本

という方は、
・かっこいいコード進行108
・決定版 コード進行スタイル・ブック
この2つの本をお勧めします。
かっこいいコード進行108
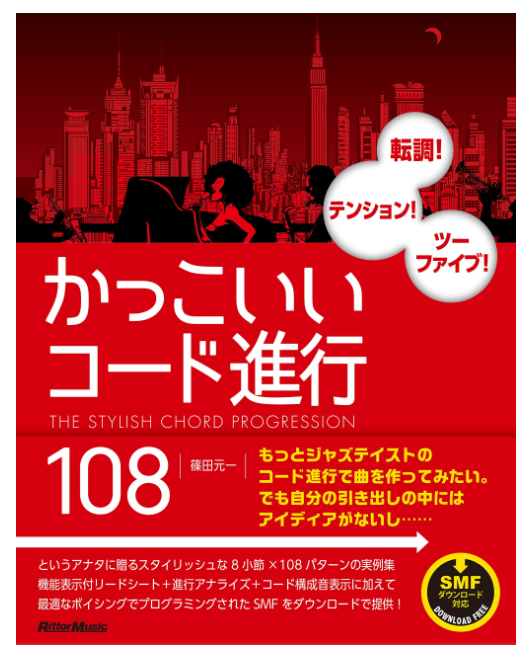
かっこいいコード進行108は、
コード進行の例が108個紹介されてある本で、今はやりのR&Bやジャズに特化したコード進行をメインに紹介しています。
スグに使えるコード進行レシピ
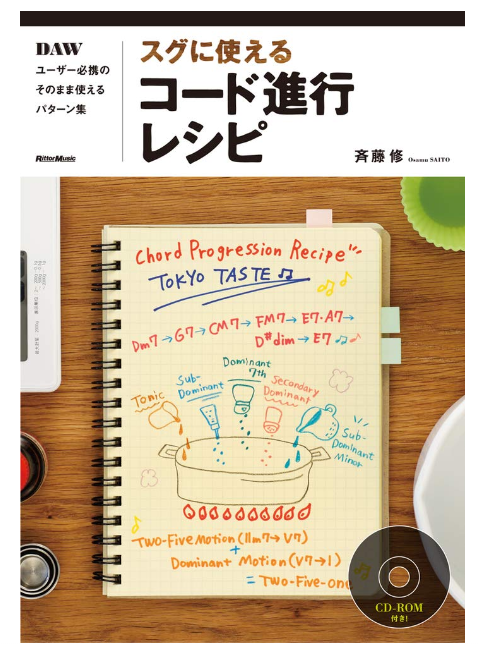
スグに使えるコード進行レシピは、
コード理論の基礎知識を紹介している本で、DTMerに向けてコード進行をMIDIデータにてダウンロードできるつくりなので分かりやすくコードについて学ぶことができる本です。
コード進行の王道進行

という方に向けて王道進行も紹介していきます。
代表的な王道進行
・Ⅳ→Ⅴ→Ⅲ→Ⅵ
・Ⅵm→Ⅳ→Ⅴ→Ⅰ
・Ⅳ→Ⅰ→Ⅴ→Ⅵm
・Ⅰ→Ⅴ→Ⅵm→Ⅳ
・Ⅰ→Ⅴ→Ⅰ
・Ⅰ→Ⅳ→Ⅰ
・Ⅰ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅰ
このダイアトニックコードの構成にキーを当てはめて、みると馴染みのあるコード進行ができると思います。
コードが作成できたら次にメロディですね。次にメロディについても少し解説してきます。
メロディの作り方
メロディにも作成するときのコツがあります。
メロディの作り方については別記事で解説していますので下記に貼っておきます。
-

-
【作曲する人向け】メロディの理論的な作り方【3つの知識が重要】
続きを見る
音楽理論の学習は必要?
コード進行を学んでいくと
音楽理論は必要なのかな?
と考える場面が出てくると思います。
音楽理論の必要性については、別記事で解説していますので下記に貼っておきます。
-

-
音楽理論いる?いらない?【いる人、いらない人の特徴を解説】
続きを見る
音楽理論について学びたい方は下記の記事から学べます。
-

-
音楽理論を分かりやすく説明するサイト
続きを見る